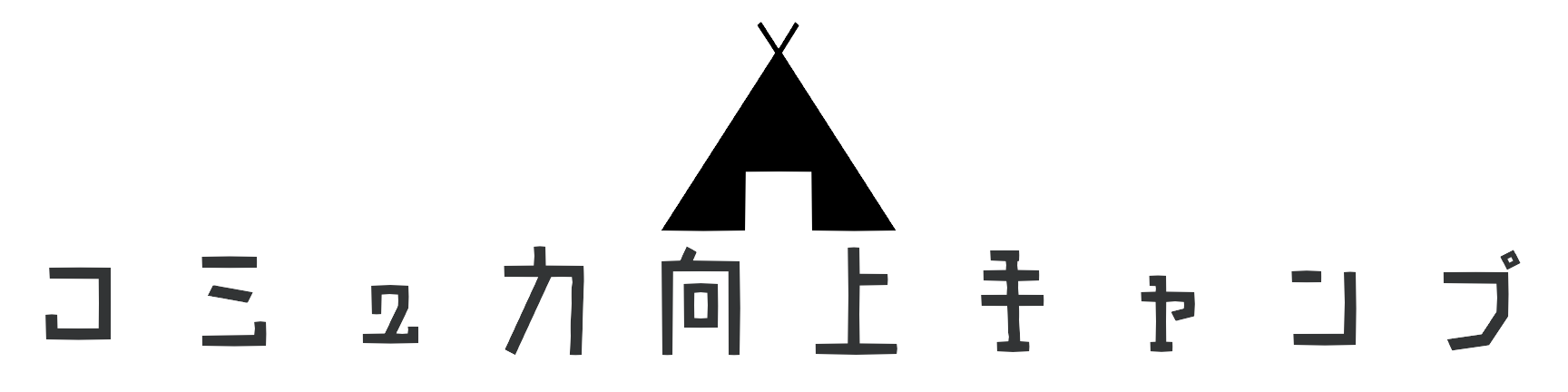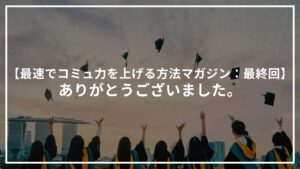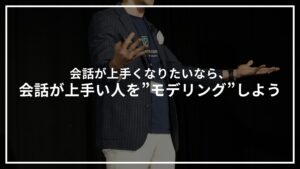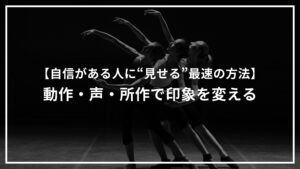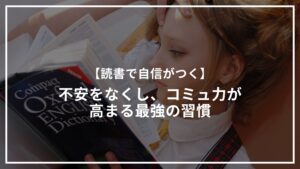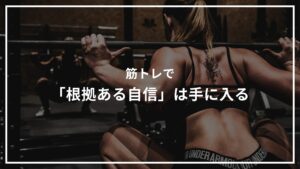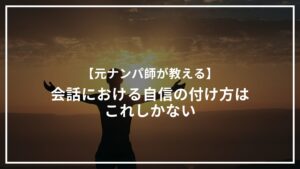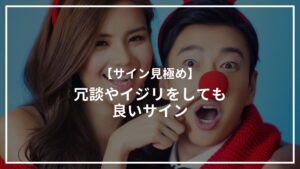KY
KYこんにちは。KYです。
https://ky2blog.com/profile/
▼ブログ版はコチラ


▼note版はコチラ


▼前回記事はコチラ
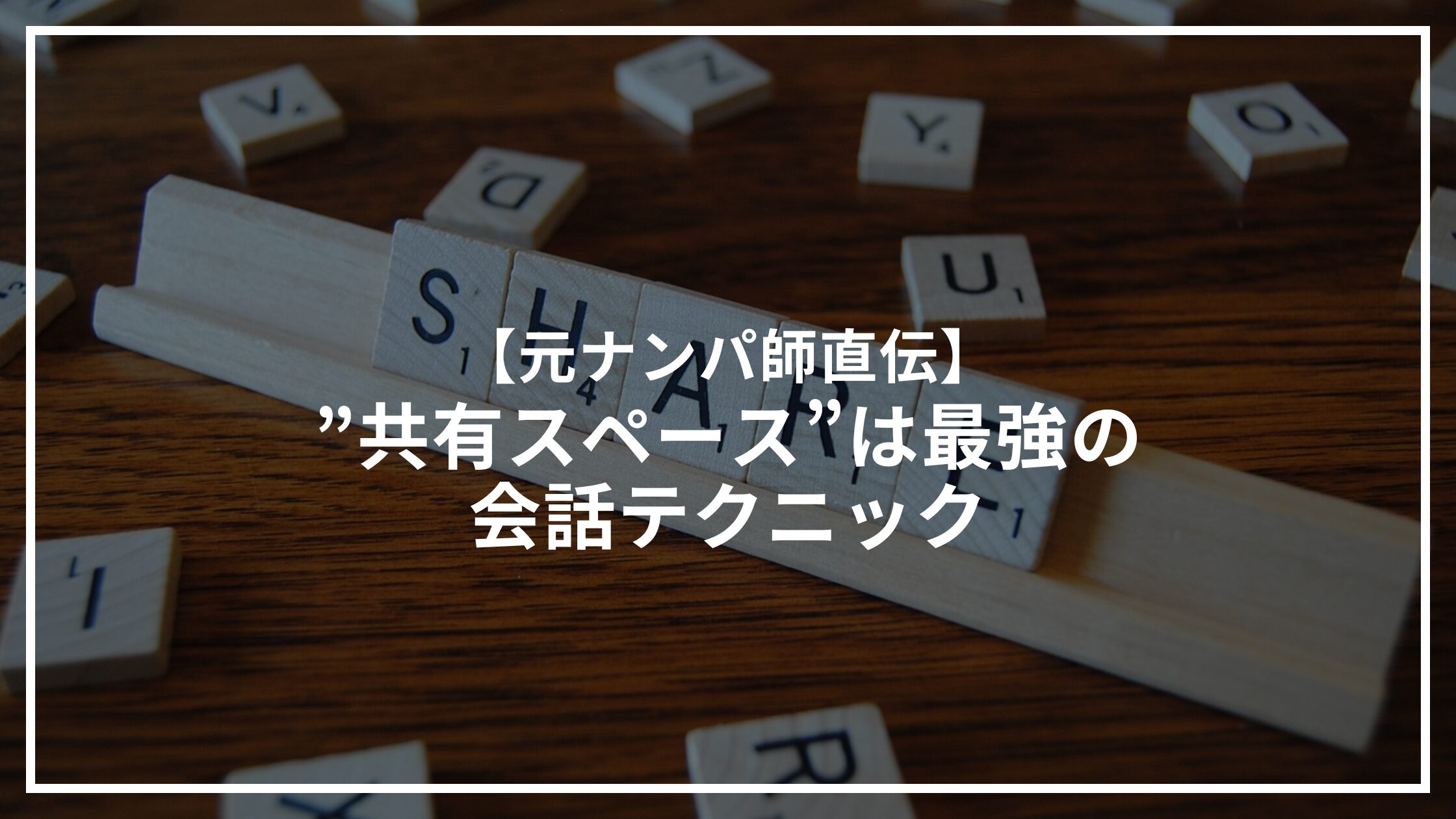
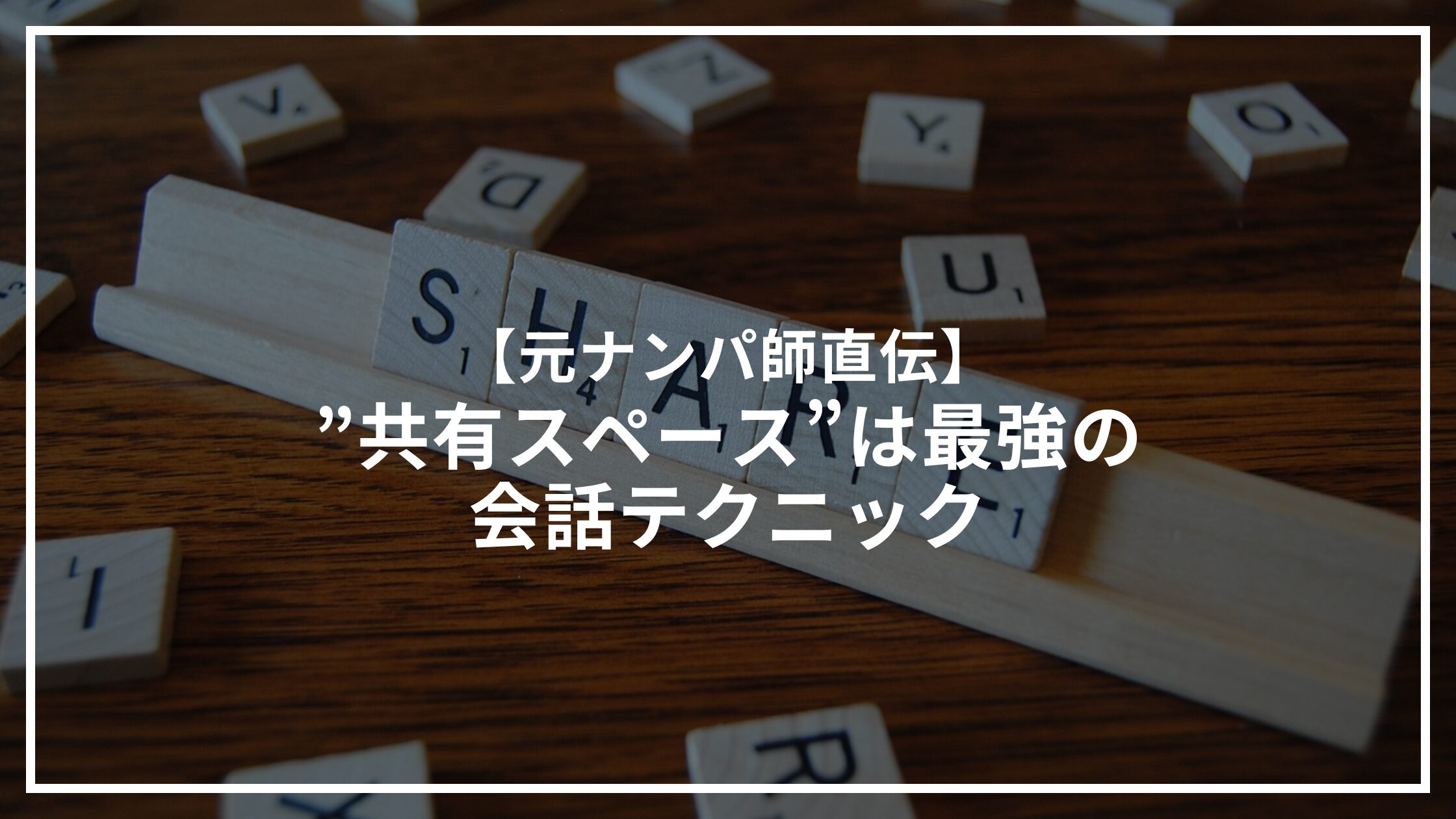
今回は、アイスブレイクのテクニックの一つ、
相手の心を開くための自己開示、自虐ネタの方法
について徹底解説していきます。
前回は「共有スペース」について紹介しましたが、今回はもう一つのテクニックである「自虐ネタ」について深掘りしていきます。
それではいきましょう。
自虐ネタを行う意味
まず、自虐ネタとは何か、なぜ使うのかについて考えてみましょう。
自虐ネタの目的は、こちらが笑える恥ずかしい話、情けない話をすることで自己開示することで
相手に心を開いてもらい、こちらが質問・話の深掘りをした際に相手に話しやすくなってもらうため
です。
自虐ネタで自分をあえて落とすことで、相手に
「この人、わざと自分のことをネタにして笑いをとっているし、この人になら自分のことを少し話してもいいかも」
と思ってもらえるのです。
アイスブレイクの段階でこうした自虐ネタを使うことで、のちのち質問していった際に相手から深い話(自分の悩みとか、好きなことなどパーソナルな話)を引き出しやすくなります。
つまり、自分を落として笑いを取るという行為は、すべて相手の心を開いてもらうためなのです。
相手の心を開くことで、より深い話ができるようになり、最速で「冗談を言い合える関係」へと発展させることができます。
このアイスブレイクのテクニックの一つが、前回紹介した「共有スペースから会話を始める」方法でした。
目の前にあるものに対して話すことは、相手にとって反応しやすいからですね。
その共有スペースの話題から、自然に自虐ネタへとつなげていく。
これがアイスブレイクの真骨頂です。
誤解:自虐ネタを言ったから嫌われる、ナメられる
よくある誤解として、
自虐ネタを使ったら、相手からナメられるんじゃないか?嫌われるんじゃないか?
ということがあります。
「え、こいつそんなことするのかよ」
みたいな。
ですがむしろ、自虐ネタでサラッと自己開示をすることで、親しみやすさが増し、相手にとって話しやすい雰囲気を作ることができるのです。
これまでこのブログやこのマガジンで書いてきた会話のキャッチボール、話題から逸れない(マジカルバナナ)のような基本の会話テクニック、そして洗練された身だしなみがしっかりできていれば、
「こんなに見た目が洗練されているのに、自分をわざと落として笑いを取ることができる人なんだ。すごいな」
と、相手に良い印象を与え、相手もあなたに心を開いてくれるようになります。
こうした話し方をする人は少なく、特に男性が女性に対して話す場面では、男性はつい自慢話をしてしまいがちです。
だからこそ、自虐ネタを使うことでそういった周りの人とは大きな差別化ができるのです。
差別化ができれば、相手はより
「この人は他の人と違って自慢話をしない。話しやすいな」
と思ってくれます。
このような理由から、アイスブレイクとして自虐ネタを積極的に行うべきなのです。
自虐ネタの条件
ただし、人からウケる自虐ネタにはいくつかの条件があります。
①笑えるものにすること
例えば、黒歴史の話や、生理的に受け付けない内容はNGです。
×悪い例:「足が臭い」「ワキガがひどい」「昔いじめられていた」
➡︎こうした話は、どれだけ面白く話しても相手が引いてしまうため、避けるべきです。
○良い例:「上司のことをお母さんって呼んじゃった話」「極度の方向音痴で知らない店に行ってしまったこと」
➡︎こういう風に、自虐ネタは聞いている側も笑える内容が望ましいです。
②笑えるテンションで話すこと
面白いネタでも、言い方次第で伝わり方が大きく変わります。例えば、ボソボソと暗い声で話してしまうと、せっかくの自虐ネタも面白くなくなります。
×悪い例(つまらない話し方):小さな声で「いや…実はさ…上司のこと、お母さんって呼んじゃってさ…」とボソボソ話す → 面白さが伝わらない
○良い例(笑える話し方):明るく表情豊かに「この前さ、上司のこと、お母さんって呼んじゃったんだよね笑」と、テンポよく話す → 笑いが生まれる
このように、ただ面白い内容を話すだけでなく、相手に伝わりやすい表情・テンションで話すことが大切です。
お笑い芸人がエピソードトークを話すように、表情をつけたり、少しオーバー気味に話したりすると、よりウケやすくなります。
この2つのポイント、
- 「笑えるネタであること」
- 「笑えるテンション・表情で話すこと」
を意識してください。
自虐ネタは作ってもパクってもいい
ただ、どんな自虐ネタでもいいとは言いましたが、
「そんな都合のいい自虐ネタなんてないよ」
と思う人もいるかもしれません。
例えば、僕の鉄板ネタとしては、
- いかがわしいグッズを買ったときに、間違えて実家に送ってしまった話
- マッチングアプリで会った人が実は男性で(いわゆるゲイの人)、二人きりの場で口説かれてしまった話
- 地元で友達の車を運転していたときにミスをして、海に沈めてしまった話
といった、ちょっと過激で笑えるエピソードがあります。
このようなネタは攻めてもOKで、むしろ過激なほうが笑いを取りやすいこともあります。
鋭い笑いを取れるような自虐ネタを話す人は少ないため、こうした話ができると、会話で差別化ができますし自己開示が効きます。
とはいえ、こんなぶっ飛んだ話はそうそうないですよね。笑
でも大丈夫です。
自虐ネタは作ってもいいし、人の話をパクってもOKなんです。
実は、先ほどの3つの話、どれも僕自身の実体験ではありません。
- 実家にいかがわしいグッズを送ってしまった話 → これは完全な作り話です。思いついただけのフィクション。
- マッチングアプリで会った人が実は男性だった話 → これは、昔脱毛サロンに通っていたときに、施術スタッフさんから聞いた話をアレンジしたもの。
- 友達の車を海に沈めた話 → これは本当に地元の友達が体験した話ですが、それを自分のエピソードとして使っています。
つまり、自虐ネタは必ずしも自分の体験である必要はありません。
大事なのは、
- 生理的に無理な話や黒歴史ではなく、笑える話にすること
- 笑えるテンションで話すこと
なのです。
だからこそ、パクっても作っても良いです。
・思いついたネタを記憶したりメモしたりして、使えるようにしておくこと
・もしスベったら「今のなしで笑」「え、スベった?笑」と軽く流すこと➡︎これならたとえスベっても笑ってもらえます。なので怖がらずに自虐ネタを言いやすくなります。
このようにして、怖がらずにどんどん使ってみることが大切です。
目的は「相手に心を開いてもらうこと」なので、自分のエピソードにこだわる必要も、本当のことを言う必要もありません。
あまりに露骨な嘘だとバレそうな話はやめておいた方が賢明ですが、作った話でも、他人の話でも、使えそうならどんどん取り入れていきましょう。
自虐ネタの種類
自虐ネタには、大きく分けて「エピソードトーク型」と「差し込み型」の2種類があります。
① エピソードトーク型
これは、いわゆる小話として話すタイプの自虐ネタです。
例えば、
「いや、実は俺、いかがわしいビデオを買ったときに、間違えて実家に送っちゃってさ…」
といった感じで、こちら側から話す短いエピソード的な自虐ネタです。
② 差し込み型
こちらは、会話の流れ・相槌に合わせて自然に自虐ネタを入れる方法です。
例えば、誰かに「KYさん、昔陸上部だったんだ!すごいですね!」と褒められたとします。
普通の人はだいたい「いやー、まあ、足は早かったですよ(笑)」みたいに、ちょっとカッコつけたりしてしまいますよね。
でも、ここで
「いや、実は俺、球技が全然ダメで、消去法で陸上部になっちゃったんですよ(笑)」
こうすると、相手が「え、そうなんですか?(笑)」とリアクションしやすくなり、笑いが取れて、相手に「この人話しやすいかも」と思われるのです。
自虐ネタの活用シーン
エピソードトーク型を使う場面は
- 会話がまだ温まっていないアイスブレイクの時
- 会話が沈黙してしまったとき
です。
例えば、まだ会話が盛り上がっていない段階で
「そういえば、この前、上司のことをお母さんって呼んじゃってさ…」
みたいに自然な形で自虐話を入れると、盛り上がります。
ただし、関係のない話題を突然出すと相手が「?」と困惑する可能性があるので注意が必要です。
だからこそ、今話している話題に関連した、話題から逸れない形の自虐ネタをチョイスする必要があります。
例えば、初対面で天気の話から会話が始まった時、
👨あなた「今日、あいにくの雨ですね〜」
👩相手「ほんとですね〜。」
👨「僕、雨男だから多分僕のせいなんですよね。笑」
👩「そうなんですか?笑」
👨「うん。僕、修学旅行でも友達との旅行でも僕が参加すると毎回雨で、逆に僕が風邪とかで休んだ時はめちゃくちゃ快晴だったから、絶対僕のせいなんですよ。笑」
👩「www」
みたいな感じです。
天気ならば天気に絡んだ自虐ネタ。
スポーツならスポーツ、
お店の話ならお店まで来た経路や、ちょっと拡張して「自分が方向音痴で、散々迷ってきた」みたいに
必ず、「その前までに話している話題」に絡めた自虐ネタにしてください。
天気の話なのにいきなり
👨「そういえば、この前、上司のことをお母さんって呼んじゃってさ…」
と言ったら相手は
👩「?」
と困惑することは、わかりますよね。
差し込み型を使う場面は
- 相手の発言に対して自然に返すとき
です。
例えば、マッチングアプリの初回デートで、今いるレストランについて話している場面。
女性が「このお店、ちょっと分かりづらいですよね」と言ったときに、
「ですよね。僕、方向音痴だから全然関係ない店行っちゃいました(笑)。」
みたいに、相手の話に”相槌を打つのと同じ感じ”で挟むのが、差し込み型の自虐ネタです。
要は、話題から逸れない(会話のマジカルバナナ)ように話の流れを壊さずに、自虐ネタを自然に入れることがポイントです。
このテクニックを使えば、冷めかけた会話を温め直すこともできるし、段々と自己開示していくこともできます。
特に「差し込み型」の自虐ネタは、小さなジャブを打つように、会話の中に少しずつ自虐ネタを入れていくスタイルです。
例えば、会話で昔やっていたスポーツについて話している時。
👩「KYさんは昔スポーツとかやってました?」
👨「僕は陸上やってましたね〜」
👩「え、陸上?すごいですね!」
👨「いや、実は球技が苦手で…全部逃げた結果、陸上部になっちゃいました(笑)」
という感じに相手の話に答える形で自虐ネタを差し込みます。
これに対して相手が
👩「そうなんですか?でも陸上ってすごいですよね!」
と返したら、さらに、
👨「いやいや(笑)、でも今やってるボルダリングも球技じゃないからね!笑」
というふうに繋げていくことができます。
こうして自虐ネタを差し込むことで、相手に「この人、面白いな」「親しみやすいな」と思ってもらいやすくなります。
相手も心を開きやすくなり、相手に「そういえば○○さんはスポーツ得意なんですか?」といった質問をした際、相手が答えてくれる会話量も増え、よりパーソナルな話題にも発展しやすくなるのです。
これが、エピソードトーク型と差し込み型の違いです。
使い分けができると、初対面の人でもスムーズに会話が弾み、最速で仲良くなることができます。
ちなみに、僕自身もこのテクニックをよく使っています。
このテクニックは、慣れるまではシミュレーションが大切です。
積極的に友達や親しい人との会話で試してみると、自然に使えるようになります。
実際に試してみると、「あ、この話はウケるな」と実感すると思います。
ウケなければ次回からやらなければいいだけです。
また、1人でも練習できますよね。
ちょっと恥ずかしいかもしれませんが、現場でスッと言えるようになるので、1人でのシミュレーションは非常に効果的です。
例えば、お笑い芸人の人がバラエティで話すシーンを見て、その喋り方やテンポ、テンション、表情を何度も鏡を見ながら、あるいは独り言で練習するんです。
地道なことですが、ナンパ師の人もよくやっている練習方法なので、ぜひ実践してみてください。
まとめ
今回のまとめです。
1. 自虐ネタの目的
- 相手の心を開くための自己開示
- 自分をあえて落とすことで、相手に 「この人なら話しやすい」 と思ってもらえる
- 会話を引き出しやすくし、 最速で冗談を言い合える関係を作る
2. 自虐ネタが効果的な理由
✅ 話しやすい場を作れる→ 自虐ネタでサラッと自己開示することで、相手に安心感を与える
✅ 「自慢話をしない人」として差別化できる → 特に男性は自慢話をしがちなので、対女性には有効
✅ 話の広がりやすさ → 共有スペースと組み合わせることで、自然に会話が続く
3. 自虐ネタの条件
✔️ 笑えるネタにすること
×悪い例:「足が臭い」「過去のいじめ体験」 → 相手が引いてしまう
○良い例:「上司のことをお母さんと呼んでしまった」「方向音痴すぎて迷子になった」
✔️笑えるテンションで話すこと
× 悪い例(暗くボソボソ話す):「実は…上司のこと、お母さんって呼んじゃって…」
○ 良い例(明るくテンポよく話す):「この前さ、上司のことをお母さんって呼んじゃったんだよね(笑)」
4. 自虐ネタは作ってもOK
- 自分の実体験でなくても使える
- 友人のエピソードをアレンジしたり、完全に作り話でも問題なし
- 大事なのは「面白いかどうか」
5. 自虐ネタの種類
✅ ① エピソードトーク型
→ 短いストーリーを話すタイプ
例:「実は、いかがわしいグッズを実家に誤配送しちゃったことがあるんだよね(笑)」
✅ ② 差し込み型
→ 会話の流れで自然に挟むタイプ
👩「このお店、ちょっと分かりづらいですね」
👨「ですよね!僕、方向音痴だから全然違う店に行っちゃいました(笑)」
6. 自虐ネタを活用する場面
☑ アイスブレイク(初対面・会話が温まっていないとき)
☑ 沈黙ができそうなとき
☑ 相手の発言に対するリアクションとして(差し込み型)
7. 自虐ネタを効果的に使うポイント
🔹 会話の流れを壊さないようにする(マジカルバナナの原則は守るように話題を繋げる・話題から逸れない)
🔹 事前にシミュレーションをしておく(一人で声に出して練習)
🔹 ウケなかったら軽く流す(「今のなしで(笑)」など)
次回は、「アイスブレイクの後、相手の心を開いていって相手の話を深掘りしていく会話テクニック」についてお話ししていきます。
「傾聴の仕方」や「相手の話を引き出す方法」にフォーカスしていくので、ぜひ楽しみにしてください。
ではまた